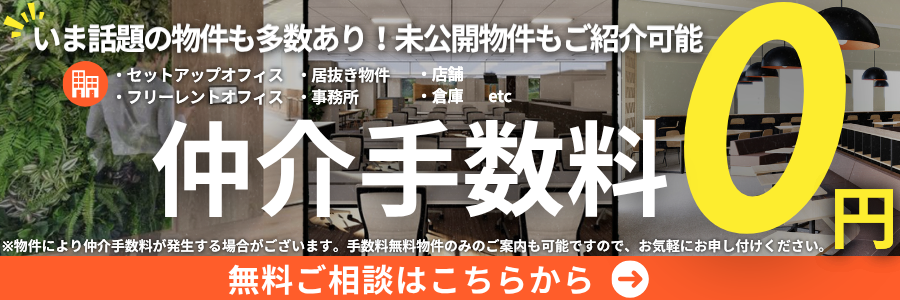不満を設計図に変えた本社移転──野村不動産グループ3,400人が実証した“出社したくなるオフィス”のつくり方
不満を「設計図」に変えた野村不動産グループの本社移転が示す、次世代オフィスのヒント
ハイブリッドワークが定着しつつある現在、「オフィスは本当に必要なのか」「出社する意味をどう設計するか」は、多くの企業のバックオフィス部門にとって重要なテーマです。そんな問いに対し、極めて実践的な答えを示したのが、野村不動産グループによる本社移転プロジェクトです。
同社グループは2025年8月、約50年にわたり拠点としてきた新宿野村ビルから、港区・芝浦の大規模複合開発「BLUE FRONT SHIBAURA」へ本社を移転しました。対象人数は約3,400人、グループ8社、最大25か所に分散していた拠点を集約するという、まさに“巨大プロジェクト”です。
※本記事の作成にあたっては、野村不動産グループの取り組みを紹介した公開情報・記事(Lifehacker JAPAN掲載記事等)を参考にしています。
約10年かけた複合開発と「自社実験」という発想
BLUE FRONT SHIBAURAは、野村不動産とJR東日本が手がける、区域面積約4.7ヘクタール、延床面積約55万㎡というグループ史上最大級の複合開発です。オフィス、ホテル、商業施設、住宅を一体で開発し、都市と働き方を再定義する試みでもあります。
注目すべきは、単なる最新オフィスへの移転ではなく、「自社実験」として設計された点です。野村不動産グループは、2022年10月から約2年半にわたり、移転対象となるすべての部署で「トライアルオフィス」を実施。現場で出た不満や違和感を徹底的に拾い上げ、それを新本社の設計に反映させていきました。
通勤時間が増えても出社率が落ちない理由
移転によって、社員の平均通勤時間は片道約20分増加しました。一般的には出社率低下の要因になりがちですが、同グループでは移転前とほぼ変わらない出社率を維持しています。
その背景には、「出社しなければできない体験」を空間として丁寧に設計したことがあります。
可変性を前提とした執務スペース
執務エリアでは、オリジナルの可変家具「UZU家具」をはじめ、用途に応じてレイアウトを変えられる什器を採用しています。固定席や明確な仕切りを極力排し、有機的な配置によって、自然と人が交わる設計です。
業務内容やチームのフェーズに応じて空間を変えられるため、「今日はどこで、誰と働くか」を社員自身が選択できます。これは、テレワークでは得られないオフィスならではの価値を生み出しています。
来客エリア「GREAT JOURNEY」による体験設計
来客エリア「GREAT JOURNEY」は、「旅」をコンセプトにした遊び心あふれる空間です。会議室は「Villa(別荘)」に見立てられ、行きと帰りで異なるルートを通る回遊動線を採用しています。
従来の「暗く、単調な会議室」という不満を、何度訪れても新しい発見がある体験へと昇華させており、来客満足度の向上だけでなく、社員の気分転換や創造性にも寄与しています。
内階段が生む、縦のコミュニケーション
フロア間をつなぐ内階段を4か所設置したことで、フロアをまたいだ移動が活発になりました。エレベーターに頼らず自然に人が行き交うことで、部署を越えた偶発的なコミュニケーションが生まれています。
実際に社員からは「社内の歩数が増えた」「以前より人と話す機会が増えた」といった声も上がっています。
会話を誘発する執務エリア内カフェ
執務エリア内には、合計15か所のカフェスペースを点在配置しています。入口付近、窓際、動線上など場所ごとに役割が異なり、利用するたびに異なる人と出会う設計です。
単なる福利厚生ではなく、「会話を生む装置」として位置づけられている点が特徴です。
担当マーケターの視点
野村不動産グループの本社移転で特筆すべきは、「オフィスを完成形としてつくらなかった」点にあります。2年半に及ぶトライアルオフィスは、社員をユーザーとした徹底的なUX検証であり、そのプロセス自体が強力なインナーブランディングになっています。通勤時間が伸びても出社率が維持されている事実は、「立地」や「制度」以上に、「体験価値」が人の行動を左右することを示しています。バックオフィス視点で見れば、本事例は単なる移転成功事例ではなく、採用力向上、生産性、エンゲージメントを同時に高める“経営施策としてのオフィス”の好例です。オフィス移転をコストではなく投資と捉える企業にとって、多くの示唆を与えるプロジェクトだと感じました。
無料相談で理想のオフィスを見つけましょう
東京オフィスチェックでは野村不動産グループ系のオフィスビルもご紹介しております。
話題物件は早めに成約することが多々ありますので、興味があれば早めにお問合せください。